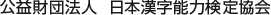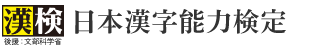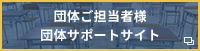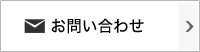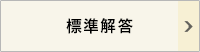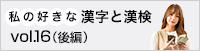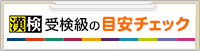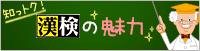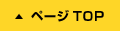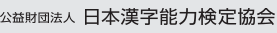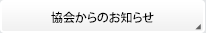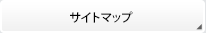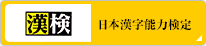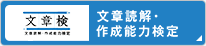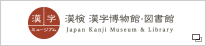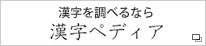大学・企業の漢検取組事例
教員の漢字語彙力・日本語運用能力について

大学・短期大学・専門学校 / 大阪
[大学] 大和大学
教育学部 国語教育専攻 教授 舟橋 秀晃 博士(教育学)
■ 国語を教える教員(小・中・高)に求める漢字語彙能力、日本語運用能力
国語の平成29年版学習指導要領は、とりわけ漢字について(〔知識及び技能〕⑴)、小学校では「学年別漢字配当表」の当該学年の漢字が読めることと漸次書き文や文章の中で使うこと(各学年エ)、中学校では前学年までに学んだ「常用漢字」を読み「学年別漢字配当表」の漢字を文や文章の中で使い慣れること(1年イ・2年ウ・3年ア)、高等学校では「常用漢字」の読みに慣れ、その主な漢字を書き文や文章の中で使うこと(現代の国語ウ・言語文化イ)ができるようになる指導を教員に求めています。
また語彙については、中学校では「理解したり表現したりするために必要な語句の量を増し、慣用句や四字熟語などについて理解を深め、話や文章の中で使うとともに、和語、漢語、外来語などを使い分けることを通して、語感を磨き語彙を豊かにすること」(3年イ)、高等学校「現代の国語」では語句や語彙の構造や特色、用法及び表記の仕方などを理解すること(エ)、「言語文化」では我が国の言語文化に特徴的な語句の文化的背景について理解を深めること(ウ)、「古典探究」では古典に用いられている語句の意味や用法を理解すること(ア)などができるようになる指導を教員に求めています。
いずれにせよ、児童生徒にそれらを指導するには、国語を教える教員自身に、各学年の国語教科書を隅々まで理解し使用できる充分な漢字語彙能力と日本語運用能力がきちんと備わっていることが、大前提となることは言うまでもありません。
■その前段としての教員養成課程生に求める漢字語彙能力、日本語運用能力と、大学入試で問うている力
したがって本学で国語の入試では、学部・学科を問わず常用漢字表の範囲内で、漢字の読みや、同訓異字・同音異義語の判別ができるかどうかを問うています(漢検準2級~2級レベル)。また、特に教育学部教育学科国語教育専攻の入試では、常用漢字の読み書きを、送り仮名も含めて記述できるかどうかも問うています(漢検2級レベル)。
■本学の取り組み(資格取得報奨金制度)※2024年度実績(内容は毎年度見直されます)
いま多くの大学では「三つのポリシー」(アドミッションポリシー/カリキュラムポリシー/ディプロマポリシー)を入学志望者や学生に示しています。本学では、これとは別に独自の取り組みとして「進路目標」を学部・学科ごとに定め、その点からも、学生が4年間で自身の資質・能力を高められるようなサポートを実施しています。
教育学部の「進路目標」は、「教員採用試験全員合格をめざします」「国語教育専攻、数学教育専攻、英語教育専攻においては、全学生90名の内、高等学校教員採用試験に60名以上、中学校教員採用試験に30名以上の合格をめざします」の二つです。
このサポートの一環として、教育学部初等幼児教育専攻と国語教育専攻では漢検1級取得者に5万円、漢検準1級に3万円などの報奨金を用意し、あくまで任意で高い水準の資格取得をめざす学生の志を応援しています。毎年度、数名の受給者がいます。
学習指導要領の求める水準に照らせば、本学入試で求める漢検2級レベルに達していれば、国語の教員として既に必要十分な能力に達しています。とはいえ、今後もし中高一貫校や高等学校で古典的文章や戦前の文学などを多く扱う教員として勤務していきたいのであれば、在学中に、漢検準1級や1級をめざしてさらに己の素養を高めていきたいところです。本学の資格取得報奨金制度は、そのような見地からレベルを設定しています。
■ 国語を教える教員(小・中・高)を目指す学生に一言
「スマホで漢字を選べばそれで大丈夫、自分で書く必要はない」「分からない言葉があってもコンピュータが読み上げ、意味も教えてくれる」という意見があります。しかし、ほんとうにそうなのでしょうか?
大学は高等教育を受ける場所であり、自ら勉学しに来るところです。そしてAIが一層普及する近未来に少子化を迎える日本においては、望めば誰もが高等教育を受けられるような教育環境を整えていかないと、そのうち簡単な労働や単純な知的生産がみなAIに置き換わることによって、社会参加を阻まれてしまう人々がかえって増えていくに違いありません。
これからの日本の児童生徒たちには、こんな世の中だからこそ、高等教育にスムーズにアクセスできるよう、小学校のうちから従来以上に漢字に親しみ、抽象概念を漢語で理解できる思考力が必要不可欠です。日本中の人たちが今、教員の指導力に大きな期待を寄せているのは、こうした近未来がいよいよ現実のものになりつつあるからなのです。
教員をめざすみなさん!まずは大学入試を突破することが大事ですが、それだけでなくその先に、大学でどのような学びが待っているのかを、今のうちからぜひ想像してみてください。しかもその学びを、今度は自分が、小中高の教員として培う側に回るのです。このことを強く意識しつつ目の前の学習に果敢に挑んでいってほしいと、強く願っています。
■略歴
教育学部 国語教育専攻 教授 舟橋 秀晃 博士(教育学)
広島大学大学院教育学研究科(博士課程後期)修了 日本国語教育学会理事 日本教科教育学会投稿論文審査委員 日本読書学会編集委員(査読者) 光村図書中学校国語教科書編集委員
滋賀大学大学院教育学研究科(修士課程)在学中に高校で2年、修了後は中学校で20年、教壇に立つ。滋賀大学教育学部附属中学校教諭・研究主任を経て2014年、大和大学教育学部准教授。2018年博士号取得、同年より教授。単著に『言語生活の拡張を志向する説明的文章学習指導』(溪水社2019)。
※掲載内容(所属団体、役職名等)は取材時のものです。