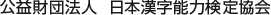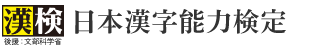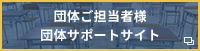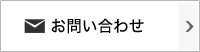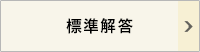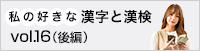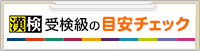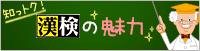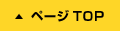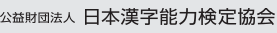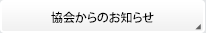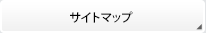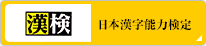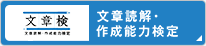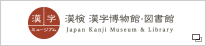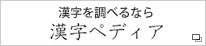団体受検 取組事例(小・中・高 等)
小学校
漢検を通じて漢字力が効果的に身に付く。毎年延べ約3割の児童が漢検に挑戦。/小学校/愛知
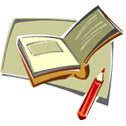
中部 / 愛知
[公立] 小牧市立陶小学校
教務主任 奥田 敏晴 先生
漢検導入を検討し始めたのは、市内のある中学校で「毎年最低1回は受検しよう」という取り組みを行い、「漢検を定期的に実施していくと、漢字力・国語力向上という成果が出る」という話を聞いたからでした。その後、協会発行の『漢字学習ステップ』を自分で購入し、それに沿って実際に勉強してみました。それまでは若干の苦手意識を持っていた「部首」についても自然に学べる内容となっており、「部首を覚えれば、単純な反復練習をさほどしなくても確実に漢字が覚えられる」ということを体験しました。例えば「隷」という漢字は一見複雑で覚えにくそうですが、「武士の士」と「示す」と「健康の康の中(れいづくり)」という組み合わせと考えれば簡単に覚えられる、ということです。こういった話を児童にしてみたところ、とても興味を持った様子でしたので、漢検の学習は漢字習得において有効だという確信を持ち、導入を決めた次第です。
いきなり、全児童にというわけにはいきませんので、とりあえず希望者を募る形で年3回(春・秋・冬)を学校行事や授業に影響のない日曜日に実施することにしました。日曜日は公開会場の検定日と重なりますので、級ごとの時間的な制約はありますが、なんとか時間設定をやりくりして実施しています。校内実施を始めてから3年になりますが、児童の人気や保護者からの支持もあり、毎年延べ約3割の児童が受検しています。
校内での募集は、学校で作成した「漢字検定のお知らせ」というプリントを全家庭に年3回配布し行っています。このプリントは申込用紙も兼ねており、保護者や兄弟姉妹も同時に(合計4名まで)申し込める形になっているので、そういった方の申し込みも年に数名程度あります。また、年度当初の朝会で「漢字を習得すると全ての学習がしやすくなる」という話や、「部首を覚えるとその組み合わせとしての漢字が覚えやすくなる」といった話をしています。漢検に取り組む意義を説明した上で、全家庭に漏れなく案内し、児童はもとより家族にも受検機会を提供するという形をとっているわけです。

写真1:クラスでの児童の様子 漢検挑戦を決めた児童のほとんどは、協会発行の『漢字学習ステップ』などを購入し、真剣に学習に取り組んでいます。検定日が近づいてくると、自習の時間に「漢検の問題集をやってもいいですか」と聞いてくる児童もいるほどです。また、児童と共に受検する保護者の中には「今回3級に合格したので、来年度は準2級を受けます」というように挑戦を続けていく方もいます。

写真2:学校の様子 今後はなるべく多くの児童、できれば全員が年に1回は漢検に挑戦している状態に近づけられればと考えています。漢字力・国語力は全ての学習の土台であり、社会に出てからも一生使うものですから、一人でも多くの児童に確実に習得させたいと願っています。さらに、保護者や兄弟姉妹の参加も促していきたいと思っています。
※掲載内容(所属団体、役職名等)は取材時のものです。